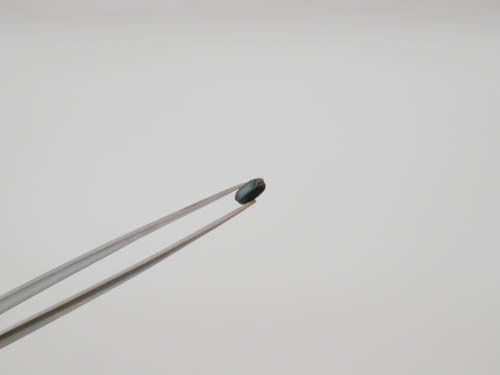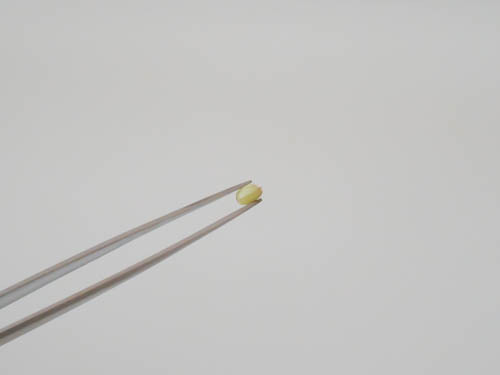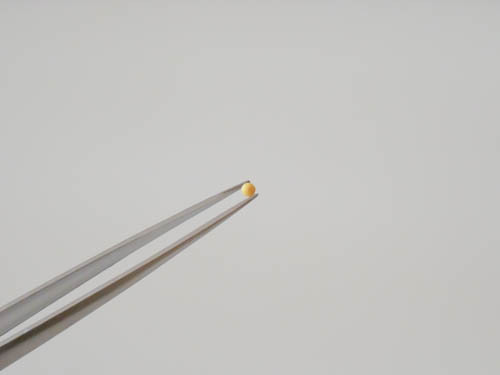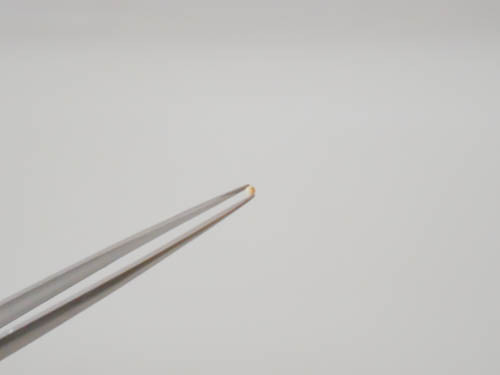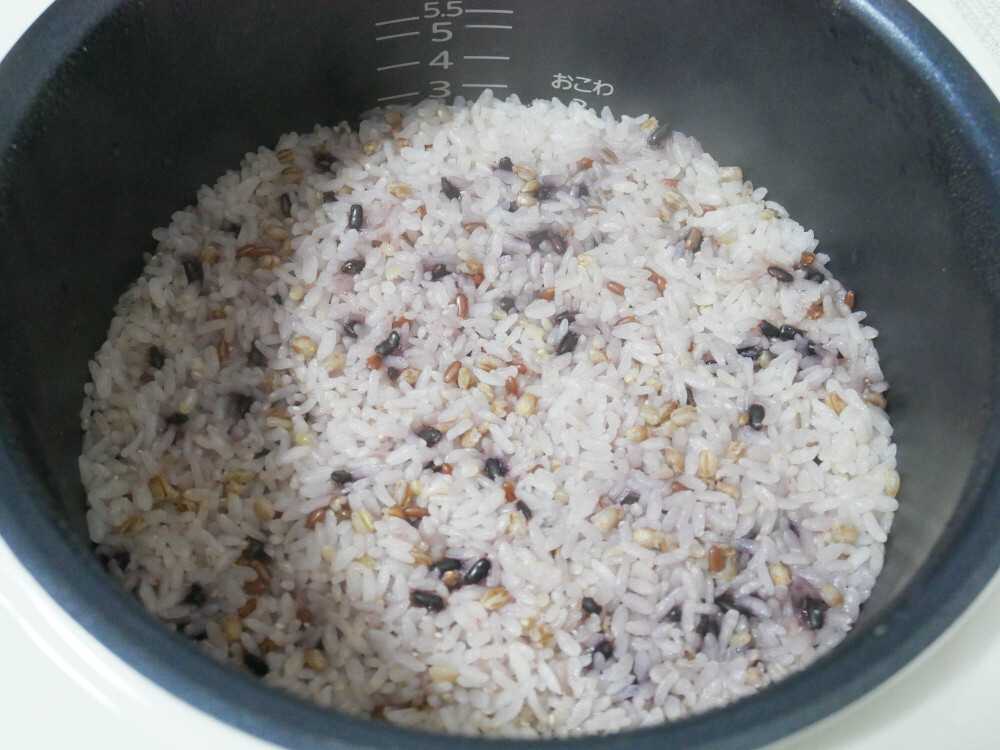【総合部門】2025生産者ランキングを発表🎉
今年も美味しい出会いやあたたかい交流を通じて、記憶に残る体験を届けてくださった生産者の皆さん。日々、美味しいものを届けたいと、ユーザーさんと向き合い続けるその皆さんへ感謝と敬意をこめて、今年も生産者ランキングを発表させていただきます❗今回はポケマル史上初の殿堂入り生産者さんも誕生です✨それではランキングを発表します❗ポケマル初✨殿堂入り&総合部門から…※ランキングは販売数とごちそうさま投稿率、評価点を指標に算出しています(殿堂入りの生産者さんはランキング対象外)ーーー✨総合ランキング殿堂入り✨ーーー 👑二宮昌基さん🎉この度はポケットマルシェ初の殿堂入りという名誉を賜り、ありがとうございます。これもひとえにご購入してくださった皆様のおかげだと思っております。今後もさらにお客様のご要望にお応えできるように頑張っていきますのでよろしくお願い申し上げます。また、今回の殿堂入りを記念して各種お得な商品を年末年始用にご用意いたしておりますのであわせてよろしくお願い申し上げます。二宮昌基さんのページはこちら!ーーーー✨総合ランキング✨ーーーー🥇第1位 薄羽哲哉さん🎉ベテランのパートさんパワーも借りて家族総出で鶏・卵を育てています。小さな子供も安心して食べることができ、買った人も、もらった人も喜んでいただける美味しい卵を作りたい、そんな想いで今日も農場をバタバタと走っています。プロフィールページのポケマルでの軌跡もチェック!薄羽哲哉さんのページはこちら!🥈第2位 吉田匡宏さん🎉青森県の大自然の中で、にんにくとりんごを栽培している農家です。土づくりにこだわり、栽培方法にこだわり、安全性にこだわり、どんなに収益性が悪くても、どんなに経費がかかっても、心から自信を持ってお届けできるものを、正直につくっております。皆様からの「美味しい!」「ごちそうさま!」の一言で、私たちは今日も頑張れます。吉田匡宏さんのページはこちら!🥉第3位 菅野千秋さん🎉「やっぱり我が家のりんごはうまい!」と“江刺リンゴ”の魅力にひかれ就農しました。私たちの作っているものは、色艶の“美しさ”、芳醇な“香り”、溢れ出る果汁&シャキッと食感“新鮮”、甘酸バランスのとれた濃い味“コク”が特徴です。お客様の心に感動を与えるリンゴを作っています。菅野千秋さんのページはこちら!第4位 山本康平さん🎉果物に満ち溢れ、果樹の並ぶ農園の景色は私の誇りで、木々の命を引き継ぎたいという気持ちから農家となりました。和歌山市の山東地域で果樹を栽培して、皆さんに美味しい!こんなの食べたことない!と”感動”をお届けできるように日々頑張っています。山本康平さんのページはこちら!第5位 藪内晃幸さん🎉みかんで感動を!!をモットーに美味しいみかんを届けれるよう日々栽培しています。サラリーマンをしていた時、叔父の栽培している有田みかんを食べて感動しました。こんなみかんを自分でも栽培したいと強く思うようになり、就農を決意し和歌山へ移住しました。量より質を優先しており、みかんの栽培に一切の妥協はいたしません。みかんで感動していただけるように全力で栽培しています。藪内晃幸さんのページはこちら!第6位 竹下誠一さん🎉日々やさいの気持ちを感じています。「人に、自然にやさしい、野菜への思いやり、高原の清涼な風や空気や水までお客様の元へ届けたい。」 それが私たちの思いです。竹下誠一さんのページはこちら!第7位 植田大さん🎉静岡のお茶処、牧之原でお茶の栽培・製茶・包装の一貫製造をしています!お茶の完成像を考えたお茶栽培と製茶技術を更に磨いていくため、毎日お茶と触れ合っています。全国の皆さんにもっともっとお茶の事を知ってもらい、気軽に楽しんで頂けるように努めていきたいと思っています!どの商品もお茶農家・茶師として品質に対する誇りを持ち、仕上げさせていただいております。植田 大さんのページはこちら!第8位 中島康範さん🎉野菜作りでいちばんこだわっているのは、根幹となる『土』です。排水性向上のためヤシの木くずをブレンド、酵素栽培&減農薬etc...食べていただくあなたに『おいしいっ!』と感じていただくことを目標に、安心安全な野菜をお届けします。中島康範さんのページはこちら!第9位 宮本大史さん🎉右も左も分からずに始めた3代目、気が付いたら千葉県なのに名古屋コーチンを飼育、さらに白鶏・赤鶏・アローカナ鶏も始めて収拾付かない小規模経営をしています!鶏にこだわり、エサにこだわり、鮮度にこだわって、消費者の皆様に「おいしい!」と言っていただけるタマゴを日々生産できるよう奮闘しています!宮本大史さんのページはこちら!第10位 数見隆一郎さん🎉由良町の美しい景観を残したい!故郷の農地を守る為に就農を決意しました。七代目農家として他の農家に研修に行きながら、仕事を習得。地元の幼馴染と共に同じ仕事ができるのは最高の励みになります。数見隆一郎さんのページはこちら!11位~15位の生産者さんはこちら🎉11位 銀山博之さん12位 梶谷高男さん 13位 新實宏太さん14位 二宮正道さん 15位 菊地桂太さん その他のランキングはこちら!推しランキング(下期)野菜・米・茶・花ランキング魚介ランキング果物ランキング肉・卵・乳・蜂蜜ランキング加工食品ランキング
- 今が旬